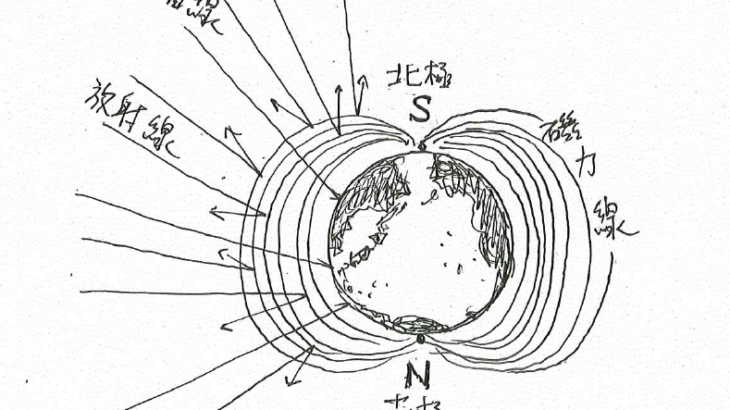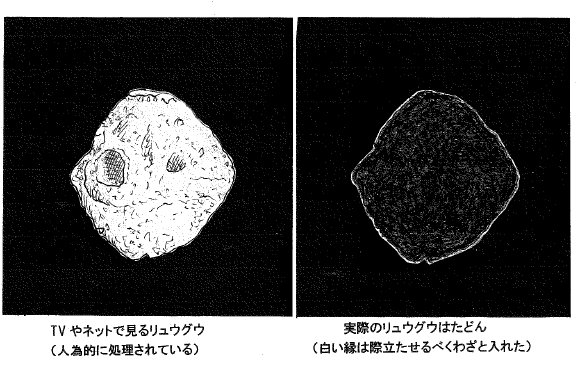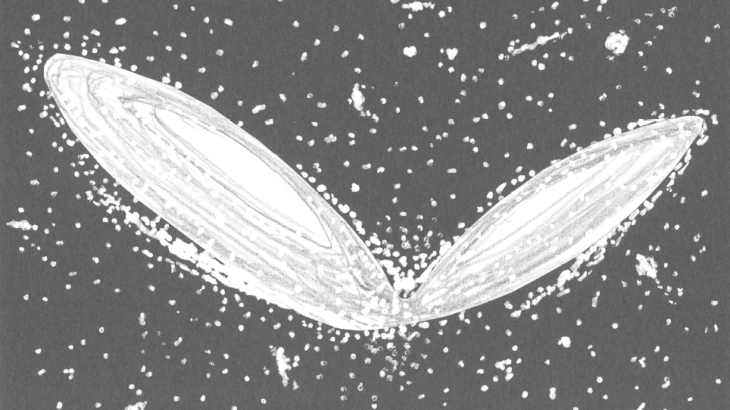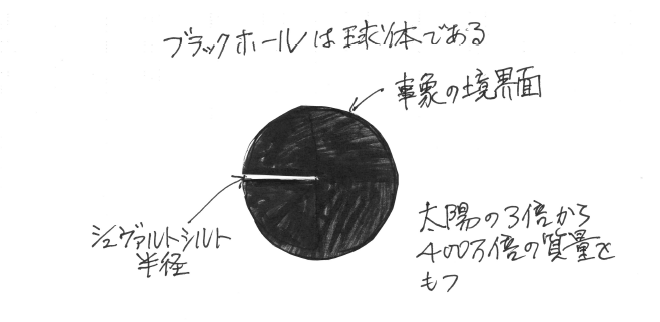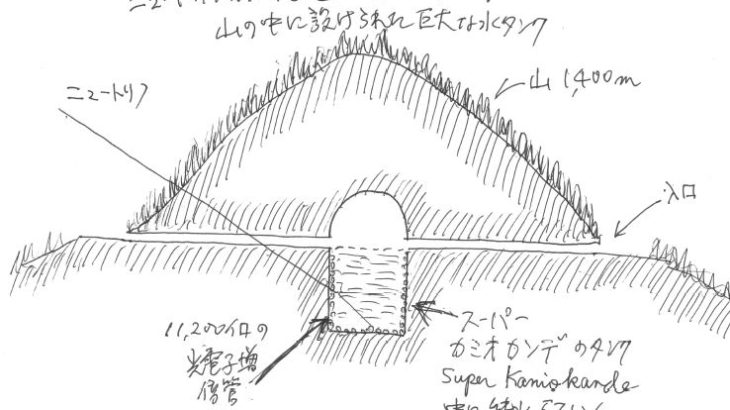「特殊相対性理論」というタイトルではなかった
1905年に発表されて世界中を驚かせた「特殊相対性理論」には、元々は異なる題名が与えられていた。
「運動する物体の電気力学について」
電気力学とは電磁気学のこと。
特殊相対性理論という抽象度の高い名称よりも、元のタイトルの方が内容をより具体的に表しているように思う。
運動する物体については、物理学の大御所ニュートンが確立した力学により、完全に記述できるはずであった。
ニュートンは揺らぐことのない権威そのものであった。
しかし、ファラデーとマクスウェルによって電気力学(電磁気学)が登場すると、ニュートン力学との間に不一致が生じてしまった。
マイケルソン・モーリーの実験もニュートン力学に疑問を突き付ける結果となった。
アインシュタインが提示したこと

ニュートン力学の矛盾の最たるものは、光の速度(C)についてである。
光速は電気力学(電磁気学)から自動的に導き出され、それは光源の速度、およびそれを観察する者の速度とは無関係に、どんなときでも、常に秒速30万kmと一定である。(C)のCは、constantという意味だ。
光、そして光速に近い速度で移動する物体については、ニュートン力学の「速度合成の法則」が全く適用できない、という矛盾である。
アインシュタインは、光速(C)が絶対であるなら、ニュートン力学が前提にする、絶対時間と絶対空間は成立しえない。
存在するのはあくまで相対的な時間と空間である、と当時の物理学者の誰もが目をむいて驚愕するような考え方を提示した。
また、光の本質は波である、というのがそれまでの物理学界の常識であったが、アインシュタインは、光は粒子であるとした。
粒子ならば、波を伝えるために必要な媒質(エーテル)の存在を考える必要はなくなる。
二重性を容認する
光は波でもあるし、粒子でもある。
この二重性を容認する、つまりどっちも正しいという、「相対的」な考え方のおかげで、例えば金属に光を当てると、光の振動数によっては金属内の電子が表に飛び出して来るという「光電効果」と呼ぶ現象をうまく説明できるようになった。
なぜなら、もし「波」の性質しかなかったら、空間的時間的に連続してホワーッと拡散していることになり、金属に当たる時のエネルギーも拡散してしまい、十分なエネルギー値をとることができないはずだ。
そこにきて「粒子」であるならば、空間的時間的にも拡散しておらず、一点にエネルギーを集中させることができるため、電子を飛び出させるほどの力を認めることができるというわけだ。
現在では、光だけでなく、電子などの素粒子や、原子など超微細なものは全て、「波」と「粒子」の二重性を持つことが分かっている。
「波」と違い、「粒子」は必ずその個数を数えることができる。
1.3とか、0.8といった小数点がつく中途半端な数値をとることはない。
連続性もないので、1個の光(光子)が持つエネルギーも、1つの塊、一定の量である。
光量子という名はここから来ている。
光を巡る本質論については、ニュートンも実は光の本質は粒子ではないかと推測していたようである。
光=粒子説の先駆者だ。
この考え方がアインシュタインに引き継がれたのだ。
二重性がもたらすもの
光が二重の性質を持つことが原因で、量子力学の特徴である不確定性が生じてしまった。
後に記すが、当のアインシュタインは、この不確定性を嫌った。
「神はサイコロ遊びをするはずがない。」という有名な台詞は、そういった彼の心情を表したものだ。
せっかく量子力学の創始者の1人となったのに、残念なことに途中でそっぽを向いてしまう。
提唱した相対論のような、どちらの意見も正しいとする柔軟な考え方をする一方で、時折とても頑迷になってしまった。
アインシュタインも人の子、ということか。